- 企業情報TOP
- コーポレートブログ〈パズル〉
- 【Vol.100】課題を価値に、ワクワクする沖縄の未来をつくる。エリアパートナーリノベース・福地組の挑戦
【Vol.100】課題を価値に、ワクワクする沖縄の未来をつくる。エリアパートナーリノベース・福地組の挑戦
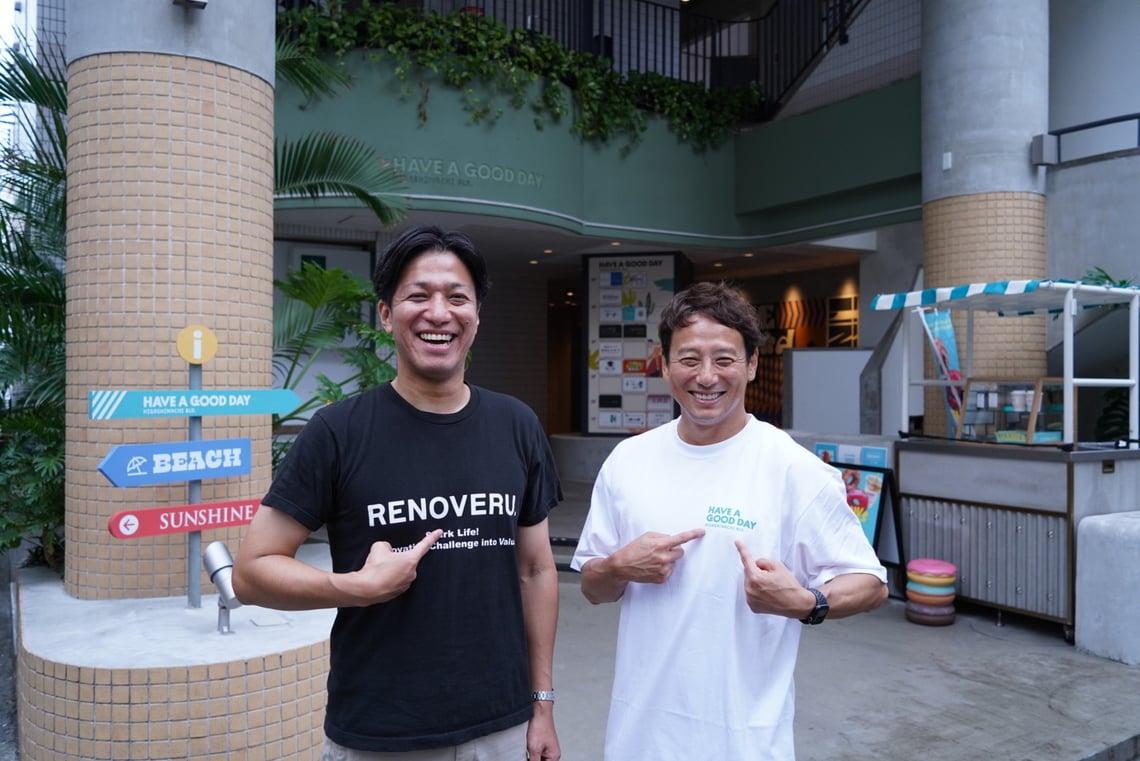
「日本の暮らしを、世界で一番、かしこく素敵に。」のミッションのもと、リノベるは統合型リノベーションプラットフォームを構築し、リノベーションをスタンダードな選択肢にすべく取り組んでいます。
中古マンション探しとリノベーションのワンストップサービス「リノベる。」は、北海道から沖縄まで全国各地にショールームを展開していますが、その4割はエリアパートナーによる運営です。
2025年3月15日、沖縄県那覇市に西町ショールームが新しくオープンしました。リノベる。沖縄のエリアパートナーリノベースが運営するショールームとしては、首里ショールーム、小禄ショールームに続く3店舗目のオープンとなります。
リノベースは、沖縄で公共工事から戸建て住宅まで幅広く手がける福地組のグループ会社です。今回は、福地組の代表取締役であり、リノベースの代表取締役も兼ねる福地一仁(ふくち・かずひと)氏に、沖縄におけるリノベーションの展望と可能性を、リノベる代表山下智弘とともに伺いました。
■プロフィール
福地一仁氏。1983年生まれ。東京大大学院修了後、三菱商事に入社。アジア向け半導体設備の海外営業に従事したのち、グループ会社に出向。その後タイで現地企業のM&Aやミャンマーへの事業展開に携わる。2018年に、家業である福地組入社。営業次長、専務を経て、2021年より株式会社福地組 代表取締役社長現職。
リノベーションには沖縄の課題を価値に変える可能性がある。
―福地組がリノベースを設立し、リノベーション事業に力を入れる背景を教えて下さい。
福地:福地組は「ワクワクする沖縄の未来をつくる」ことをミッションとして掲げています。そこには沖縄の観光地としての「ワクワク」もありますが、この島に住む住民として、楽しく快適に暮らせる沖縄をつくっていきたいという「ワクワク」も含まれます。その観点から見ても、リノベーションにはポテンシャルがあると思っています。
沖縄では、まだまだ新築志向が強く、木造だけでなく鉄筋コンクリート造の住宅でもスクラップ&ビルドが繰り返されています。環境負荷や沖縄独特の建築文化の消失を考えると、既存の建物をうまく活用し、オーナーの希望に合わせてリノベーションすることが、沖縄の地域資源や環境資源の保全を通じて社会課題に直接・間接的に価値を提供できるのではないか。そんな思いで取り組んでいます。
また、リノベースでは住宅リノベーションだけでなく、一棟リノベーション事業も展開しています。昨年オープンした「HAVE A GOOD DAY」もその一つ。スナックとコワーキングが共存する複合施設です。

▲HAVE A GOOD DAY:空き店舗が増え、「お化けビル」と呼ばれた雑居ビルを、コワーキングスペースのある複合施設へリノベーション。元々あったスナックはそのままに、新しい店舗やオフィスが入ることで新たな利用者が集まり混ざり合い、新たな価値、新たな人の流れを生み出しました。(詳細:https://have-a-good-day.okinawa/)
福地:集まる人々がコミュニティの仲間となり、地域が盛り上がり、古き良きものを守る動きにつながることを期待しています。新しい機能を付加することで地域が変わる、リノベーションの可能性を感じる事例だと思っています。

▲「HAVE A GOOD DAY」のコワーキングスペース。
―沖縄ならではの課題はありますか?
福地:沖縄は、離島だからこそ、リソースの域内循環が重要だと考えています。建築資材の調達も基本的には域外調達になるので、建設コストが上昇している今、新しい資材を県外から取り寄せてスクラップ&ビルドするのは経済的にも負荷がかかるんです。
ですが、リノベーションを選んで長く大切に使っていけば、時間軸で見ても、経済合理性の高い住宅の活用となります。沖縄という島内での循環経済の実現に向いていると思います。
また、沖縄の電力は火力発電しかないので、本州よりも資源高騰の影響を大きく受けます。今は補助金で電気代をなんとか抑えていますが、今後省エネリノベーションの提供が進めば、エネルギーコストからのインパクトを受けにくくなり、リノベーションの強みはさらに増すと思っています。
―沖縄では新築マンション価格が高騰し、沖縄住民の購入が難しくなっていると聞きます。リノベーションがその解決策になり得ると思いますか?
福地:新築コストの高騰により、実家を二世帯にリノベーションするといった需要は確実に増えています。でも、僕はそもそもの意識を変えたいと思っています。「新築が買えないから仕方なくリノベーション」ではなく、「リノベーションそのものがいいよね」という意識へと変えていきたいんです。
新ショールームでは、持ち家のリノベーションにとどまらず、将来的な売り貸しを想定した提案をする予定です。資産性の高い立地でややコンパクトな物件を安めに購入し、家族の形が変わったら売ったり貸したりできる。そんな選択肢がもっとあってもいいと思うんです。持ち家率が低い沖縄で、沖縄に住む方々に資産を還元していきたいですね。
そのためには、わかりやすい「形」という実績を作っていくことが必要ではないでしょうか。リノベーション住宅であれ、地域ににぎわいをつくる一棟事業であれ、結果をはっきりと「形」で示していくことができれば、そこに住む住民の方や、周辺の関係者に気づきを与えることができるだろうと思っています。
ここ数年、金融機関やステークホルダーの見方にも変化が見えます。山下さんも問題意識を持たれていたと思いますが、これまでリノベーション物件は、耐用年数だけを切り取って、あと何年しか持たないよという評価がされてきました。ですが、既存建物に対する資産性の評価について、マーケットのそのものの認識が変わってきていると感じます。そして、リノベーションは本来もっといろんなことができると考えてジョインしてくれるプレイヤーも実際に増えています。
変化は起こっていると思うので、具体的なモノを造って実績を積み上げていく。それだけでなく、リノベーションが生んだ価値を整理し、「だからリノベーションには意味があるんだ」とかみ砕いて説明していく。コミュニケーションしていくことが必要で、やらなければならないことだと思っています。
山下:リノベるは2010年創業で、今年で15周年を迎えますが、ステークホルダーや取り巻く状況すべてが当時と比べて明らかに変化しています。特にヨーロッパ系の投資ファンドは敏感で、環境負荷の高いスクラップアンドビルドばかりでは成り立たなくなると考えています。おそらくこの波が止まることはないでしょう。
福地さんのお話を聞いて、島であるがゆえの課題があることが新鮮でした。沖縄をあまり「島」として認識していませんでした。でもたしかに資材調達も電力供給も、「島」だからからこそ起きる課題ですね。
福地:サーキュラーエコノミーとか循環経済の視点から、さまざまな技術やサービス、テクノロジーが活用されていますが、沖縄という島しょ県だからこそ、域内調達を検討していかないといけないと思いますし、リノベーションはこうした分野と相性が良いだろうと思います。
ただ、僕は新築よりもリノベーションが良いということを主張したいわけではないんです。福地組でも新築住宅を手がけていますし、新しく造る方が良い場面も当然あります。大事なのは、新しいものばかりをよしとする価値観ではなく、まだまだ使えるものは工夫して使っていく。このバランスが取れた開発こそ、中長期的に地域の魅力を高め、持続的な発展につながると考えています。経営理念もその方向にシフトしてきましたし、金融機関や保険会社、周辺の関係者などに説明・説得していく地道な努力が今後おおいに必要になってくると考えています。
▲西町ショールームのオープンを記念し、内覧会を開催した時の一枚。1店舗目、2店舗目とは異なる新たな切り口で、若い夫婦や子育て世帯に住宅購入の選択肢を提供する。
中長期的に見る「必要性」の大切さ
―1号店である首里ショールームがオープンして5年になりますが、当時エリアパートナーになったきっかけを教えてください。
福地:リノベーションに関心を持ったのはコロナ禍前です。当時、沖縄の観光客は年間1000万人を超え、ハワイを上回る勢いでした。そんな中、沖縄で何が起こっていたかといえば、大型のリゾートホテルや高層マンションの過度な建設ラッシュです。投資目的も含め需要を超えた開発が進んでいたような印象を受けました。
僕は福地組に入社したばかりで、当時は建設会社としての立場の外側から見ているところがありました。需要があると見込んで造ってはいるけれど、供給過多にならないだろうか。競争から敗れた建物が負の遺産になって増えてしまうのではないかという懸念がありました。なにしろ、開発は一度進むともう元の環境には戻せません。
じゃあ目先の「収益性」より「必要性」を優先するなら何をすべきか。そう考えた結果がリノベーションだったんです。既存の建物を活用したり、稼働が落ちたマンションを用途変更してホテルにしたり。中長期的にはそのような開発のほうが沖縄の環境に対する負荷も少なく持続可能なんじゃないかと感じました。
山下:福地さんが三菱商事から家業の会社に戻られて間もない頃で、エリアパートナーに加盟してくれると聞いた当時は、「すごい人が現れたな」と思っていました。新築を手がけてこられたからこそ、ある意味、自己否定をしなければならない瞬間もあったかもしれませんが、「必要性」を生むためにリノベーションを使った。福地さんの取り組みは、沖縄にリノベーションという今までになかった新たな選択肢を生み出すものだったと思います。
―リノベるへの加盟を決めたのは、どこに魅力を感じたからですか?
福地:スタートは、山下社長のゼネコン時代のインタビュービデオでしたね。当時の僕は、事業をより早く広げたい、新規事業を手がけたいという思いがあり、リノベるのエリアパートナーに魅力を感じました。当時の担当の方々が、こちらの状況をしっかりヒアリングし、課題への向き合い方を共に考えながら伴走してくれたことも大きかったです。
新規事業はどうしても人の安定が欠けると回らなくなってしまうので、仕組化が重要です。そんな中、リノベるのサポート体制の手厚さは、加盟して最も助かったポイントでした。
山下:リノベるのフランチャイズ事業を全国展開するにあたって、属人的なビジネスモデルのためスケールしづらい点に悩みました。そこで、アプリやツールといった仕組みで補える部分と、人が直接関わるべき部分を分けることで、持続的に成長できるビジネスモデルをつくっていきました。結果的にこのバランスがうまく機能していると感じています。
福地:どんなに良いアプリでも使いこなせないと意味がないので、加盟後、経験やノウハウを持つ方々にしっかりサポートいただけたことはありがたかったです。
▲福地組、リノベースの福地社長。
―山下さんは、福地のどこに魅力を感じましたか?
山下:リノベーションには、ビジネスとカルチャー創生という側面があります。この二つは相反するもので、うまくまとめあげるには手間がかかるし、難易度が高いと僕は思っています。
でも福地さんは、長期的にビジネスとして成長させるために何が必要かを見極め、バランス感覚とビジネスリテラシーを高く持って取り組んでいらっしゃる。そんな福地さんが、リノベーション事業に本気で取り組んでくれているところにすごく魅力を感じるし、だからこそ速いスピードで成長されてきているんだと思います。
福地:リノベーションは、先ほどお話しした島特有の課題へのアプローチも含めて、取り組んでいかなきゃいけないこと。当然うまくいかないこともありますが、要所要所は押さえ、それを超えていくことでより価値を提供でき、大きく成長できると思っています。

▲リノベる代表の山下
体制を構築し、マーケットシェアをさらに広げたい
―今後の展望についてお聞きします。「リノベる。沖縄」として新たなショールームがオープンしました。このスピードで実質3店舗目は全国初ですね。
福地:沖縄にはまだまだマーケットチャンスがあるからこそ、強気に店舗展開を進めましたが、それだけでなく、リスクを積極的に取りにいく経験を重ねていこうという狙いもあります。
とはいえ、既存の物件を売却していけば資産は循環していくはずなので、単にリスクを積み上げることにはなりません。首里ショールームも受注件数が常に右肩上がりというわけではありませんが、資産の循環や入れ替えがスムーズにできる手応えはあります。新たなショールームでも受注件数が増えれば、資産の循環はさらに加速するはずです。
―リノベるとのパートナーシップにおいて、今後実現したいこと、期待していることは何ですか?
福地:「リノベる。沖縄」の住宅リノベーションは、沖縄のマーケット全体で見ればまだ小さなシェアにとどまっています。今後は年間のリノベーション件数をもっと増やせるように体制を構築し、シェア拡大を目指したいです。
また、住宅に限らず、事務所や店舗、クリニックなどの非住宅分野でもリノベーションの可能性は広がると考えています。たとえば、東京に本社がある企業の地方拠点の一棟リノベ―ションの施工や運営をエリアパートナーが引き受ける展開があっても面白いですよね。マーケットにニーズがあり、そこにリノベーションという手段が当てはまり、さらには地域を活性化するような事業であれば、住宅以外でもエリアパートナーとして連携してできたらいいなと思います。
僕らは沖縄全体の都市開発に疑問をもつところから課題設定をしているので、地域の魅力やエリアの価値を中長期的に高めるまちづくりとは何かを常に考えています。「HAVE A GOOD DAY」もそのなかで生まれた事業です。リノベるの都市創造事業部の一棟リノベーションも、同じようなコンセプトや考え方で取り組まれていると思うので、ノウハウや情報の共有も含めて、今後一緒に何かができればいいなとも考えています。
山下:山下:僕らも、区分マンションのワンストップリノベーションからスタートし、「まちの新しい価値になる」を掲げる都市創造事業・一棟リノベーションへと広がり、住宅とまちづくりがどんどん融合していっている側面があります。福地さんとは、一緒にプロジェクトを進めることもあれば、同業者として競争する部分もある。そうした健全な競争がつくれたら、事業として素晴らしいものになるだろうと思います。
また、「すべてをスクラップしていてはいけない」と考える投資ファンドのお客さまも増えている今、そうしたお客さまと福地さんが沖縄で新たな取り組みをする可能性もあるかもしれません。福地組のゼネコンチームとともに、新築ではなく、既存建物の躯体を手直していく、なんてことがあっても面白いですね。